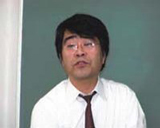ジェイソンを知らない子供たち
最近亡くなった上岡龍太郎が、落語でも講談でもない、「話を上岡風に語る」という芸をやっています。「雨禁獄」という妙な言葉があります。白河法皇が、ある行事をしようとしたところ、雨のために何度も延期することになって怒り心頭、雨を器に入れて獄舎に下した、という『古事談』にある話が元になっていますが、これを「お話」として語るのですね。あるいは、「こんな映画を見た」という内容の話。笑いをとるわけでもなく、ただ話を聞かせるというスタイルで聞き手を引きつけます。お蔵入りになった「幻の映画」のストーリーを紹介するという形で、演じた俳優の名前も明かして、最後のところで「お蔵入り」になった理由がわかります。聞いている客はみんなその映画を見たいと思ったでしょう。ところが、実はすべてフィクションで、そんな映画は実在しないのですね。もちろん、上岡はその種明かしもしないで、舞台をおりていきます。
古舘伊知郎もひたすら自分の話術を聞かせるという舞台をやっていました。たとえばお釈迦様一代記みたいな話を、何も見ないでストーリーとして語っていくのですが、しゃべることがすべて頭の中にはいっていないとできません。しかも古舘がやる、ということなので聞く者も淀みのないしゃべりを期待しています。言いまちがいも許されませんし、言葉につまるとか、「アー」や「エー」など言うのは論外です。まさに「しゃべりの一本勝負」というところで、それはまあ実に見事でした。プロレスの中継をしていたときはやたら仰々しいフレーズを使う軽薄な男、という印象だったのに、さすが「しゃべりのプロ」という感じでした。
ストーリーを語る、という点では人情話や怪談も落語のネタになると前回書きましたが、怪談は三遊亭圓朝という人が始めたと言ってよいでしょう。この人はもともと笑いをとる話もやっていたようですが、あまりのうまさに周囲だけでなく師匠にさえもねたまれ、自分がやろうとしていたネタを先に別の人がわざとやって邪魔をするということもあったそうです。そこで、他の人にはない持ちネタを作ろうということで、怪談話を始めたとか。こういう話では笑いをとるわけにはいきませんが、そうなると講談との違いが薄れてきます。声を張り上げリズミカルに言葉を発する講談に比べると、おさえたトーンでリアルな話しぶり、という違いはあるでしょうが、ネタはかぶっている場合があります。最近は神田伯山の人気によって、講談も再評価されて集客力も上がってきているようです。一方、浪曲はどうでしょうか。絶滅に近いような状態かもしれません。浪曲ファンだと言う若い人がどれだけいるのでしょうか。
一人漫才とも言うべき「漫談」という形式は細々と続いています。綾小路きみまろというビッグスターもいましたし、今はすっかり俳優になってしまった「でんでん」も分類すれば漫談だったと言えます。鳥肌実というかなりあぶない人もいました。一人でやる人としては、ダンディ坂野、小島よしお、スギちゃん、ケンドーコバヤシ、たむらけんじ、変わったところではマキタスポーツ、今はなき(?)ガリガリガリクソンとか、結構いることはいるのですが、純粋な「しゃべり」だけでなく、リズムねたであったり、コントや物真似と融合したりしていることも多いようです。「物真似」はテレビでもよくやるので、結構人気があります。コロナ禍で身動きがとれなかったころ、YouTubeを利用して、物真似芸人がいろいろと発信していました。ミラクルひかるなんて、なんとガーシーの物真似をやってましたからね。
YouTubeでは、怪談も盛んで、一つのジャンルとして定着していますが、「実話」と銘打っているものと、「創作」と名乗らないまでも、つくりもののストーリーだと思われるものとがあります。後者のほうが、意識して作っているのですから面白さは上のように思えるのですが、わざとらしくて、ウソくささが鼻につくこともあります。実話系はオチがあるわけでもないのに、妙にこわかったりします。ひと昔前、ある都市伝説がはやりました。見た者を一週間後に呪い殺す「呪いのビデオ」という話で、友達の友達の話、みたいなよくある形式になっていますが、それって小説の『リング』やがな、ということがありました。小説を読んだだれかが人に話した内容がさらに別の人に伝わっていくうちに、一つの都市伝説になってしまったのですが、元ネタがはっきりしているという点でめずらしいパターンです。
短歌の世界でも元ネタのある歌というのがあります。元の歌をふまえて新しい歌の背景とすることで、歌に奥行きや幅が生まれるというのが「本歌取り」ですが、これが有効になるのは元歌を知っているという条件があるからです。パロディも同様で、元になるものを知らないと意味不明であり、面白さも当然感じられません。ところが、本来有名でだれでも知っていたはずの元ネタが時代の変化で忘れられることもあるのですね。だいぶ以前に書いた、標語の審査に出かける父親が子どもたちに「父はヒョウゴにおもむかん」と言ったという話も、元ネタの『青葉の別れ』が歌われなくなった現在、まったく意味不明でしょう。流行語のパロディなど、元ネタが「流行」つまりやがては消えるものなので、どうしようもありません。「笑点」という番組名の元ネタが『氷点』であることも、『氷点』という作品がほとんど読まれていない現在、知らない人のほうが多いでしょう。
『バタリアン』という映画名を元にした「オバタリアン」という言葉もありましたが、いまやどちらも忘れられています。以前、生徒たちに「睡眠中、体から酸を出す昆虫って知ってる?」と聞いたところ、答えがない。「蚊や」「なんで?」「カーネル・サンダース」と言ったところ、「きょとんとしています。カーネル・サンダースの名前を知らないんですね。たしかに最近、この名前を聞かなくなりました。ちなみにくまのプーさんの本名もサンダースなんですが、これも知らないだろうなぁ。チェーン・ソーを振り回すホラー映画の主人公ジェイソンも子どもたちは知りません。「えっ、ジェイソン知らんの? 君らは『ジェイソンを知らない子供たち』か!」と言ってもさらに通じません。そりゃそうだ、そもそも元ネタの『戦争を知らない子供たち』という歌を知らないのだから。