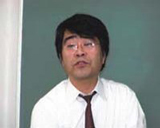どうもすみません
ことわざの授業をしていて「三人寄れば文殊の知恵」というのが出てきました。「文殊菩薩」というのは「普賢菩薩」とセットで釈迦如来の横に立ってると言うと、なるほどとうなずく者もいましたが、わからない者も多い。そこで、「菩薩」の説明をしたあと、「君らでも知ってる菩薩がある。観世音菩薩とお地蔵様や」と言うと、「お地蔵様って何?」とぬかす不届きな生徒がいたので怒りのあまり、「お地蔵様、知らんのか。『いただきます』と言ってご飯食べたあとに言う言葉や!」と言うと、すかさず「そら、ご馳走様や」と鋭くツッコミを入れる生徒が何人もいました。関西人としてすくすく育っています。北千里教室の五年生、ありがとう。
で、前回の続きですが、「漁夫の利」は原文では「漁夫」ではなく「漁父」です。しかも読み方は「ふ」ではなく「ほ」と読み、父親ではなく年寄りという意味になります…と言うのは「蛇足」ですね。「蛇足」も戦国時代の話で、居候たちが主人からもらった酒をめぐっての出来事です。主人が数人の居候に与えた酒が中途半端な量だったのでしょう。一人で飲むには多く、かといって皆で分けると足りない。そこで勝負しようじゃないか、ということになって地面にヘビの絵を描く、という話です。「居候」と書きましたが、これは「食客」としたほうがよさそうですね。この時代、有力者は食客を多く抱えて「ただ飯」を食わせていました。財力がなければできませんし、人が集まるのは人望があるから、ということになるので、食客の数が多ければ多いほど世間からの評価も高まります。千人を超える食客を抱えている者もおりました。孟嘗君などは三千人と言われます。それだけ多いと、一人一人の顔も名前も覚えられないでしょうが、中には強い恩義を感じる者もいたようです。孟嘗君を助けて、宝物を盗み返した者や鶏の鳴き真似をして関所を開けさせた者の話から「鶏鳴狗盗」の言葉も生まれました。ここから清少納言の「夜をこめて鳥の空音ははかるとも世に逢坂の関は許さじ」の歌にまで話をひろげると、百人一首を覚えさせられたという生徒などは、「おお」という顔をします。
「五十歩百歩」の話でも、その背景を知っていると、より面白く感じられます。兵士が何歩逃げたかというのはたとえ話にすぎません。梁の恵王が孟子に、「自分は、凶作のときにはその民を豊作の土地に移住させたりして、心配りをしているのに、他国からわが国を慕って人々がやってくることがないのはなぜか」と問うたときの話なんですね。小手先の対症療法をするより根本的なところに目を向けないとだめだと諫めた、という話です。こういうような細かいところに興味が持てれば知識として定着するのですね。細かい部分は入試には出ませんが、雑学として役立ちますし、そういう知的好奇心が強いとより知識が増えていきます。「神は細部に宿りたもう」と言いますが、ディテールにこだわると見えてくるものがあるのですね。
世の中にはやたらディテールにこだわる人がいます。ある映画で、時代設定のリアルさを追求していくあまり、映画の中では引き出すことのない机の中の手紙や書類まで、その時代に合わせたものを用意した、という話があります。こういう話にはしびれますねえ。初期のころの水木しげるにもしびれました。たとえば木を描くときに木の葉の一枚一枚を葉脈まで描いたり、墓石の穴の一点一点を丁寧に描いていったり、すすぼけた掘っ立て小屋の羽目板の木目までリアルに再現したりしていました。『墓場の鬼太郎』という作品が不気味だったのは、そういうディテールにこだわる画風が大きな要素を占めていました。それに対して人物の絵はなぜかスカスカ感が漂い、背景との対比がなかなか面白かった。ねずみ男なんかスカスカです。ところが、ふつうの妖怪はなぜかリアルなんですね。本来デッサン力のある人でした。
「アマビエ」という妖怪が一時期ブームになりました。でも、あの絵は下手の極致です。大人が描いたものとは思えません。だれかの絵を写したのか、その人も下手だったのか、ひょっとして字も下手だったのかもしれません。カタカナで「アマビコ」と書くつもりだったのが、「アマビエ」に見えたという説もあります。たしかに「アマビコ」なら「海人彦」という字を当てられますが、「アマビエ」ではいまいち意味がわかりません。江戸期には印刷技術も発達してきていますが、それまでの基本は写本ですね。人が写したものをまた写していく。その途中でだれかが写し間違いをしたり、どこかの部分がごっそり抜けたりする。妙だなと思っても生真面目な人ならそのまま写したり、「脱落ありか?」などのメモ書きをつけたりすることもあったでしょうが、いいかげんな人なら、つじつま合わせで勝手に適当なことばを補うなんてこともありました。同じタイトルの本でもいくつかの系統があって、食い違いが生じているのはそのせいです。
『平家物語』は平曲として琵琶の音にのせて語られるものであったという事情もあって異本がたくさんあります。その最大のものが「源平盛衰記」だと言われます。なんとタイトルまで変わってしまっています。耳で聞く『平家物語』が、読み物に移行していく中で生まれたものでしょうから、『源平盛衰記』は読み物であるはずですが、なぜか落語では『平家物語』ではなく、『源平盛衰記』になっています。これは林家正蔵の家に伝わる話なので、林家三平という人も持ちネタにしています。三平は本格的な落語はほとんどやらず、小咄的なものをつないで客席いじりをしながら笑いをとっていく人でした。ダジャレが受けないと「どうもすみません」という定番のギャグを入れたり、すべったときには「今の話がなぜ面白いかというと…」と解説したりする、今のスベリ芸のはしりみたいなことをやっていましたが、「爆笑王」と呼ばれるぐらい人気のある人でした。だから、『源平盛衰記』という話も、源平合戦というストーリーを背景にしながら、持ちネタの小咄を入れたりしていろいろ脱線していくスタイルです。で、なんとこれを立川談志が三平から習って、自分の持ちネタにしているんですね。まあ、一応は源平の戦いをテーマにして一つの話にしているわけで、こういうものも落語のネタになるところが面白いなと思います。「落語」と言っても滑稽なものだけでなく、人情話と呼ばれるものもありますし、「怪談」さえもネタになるのですから。人というのは、どんなものであれ「お話」を聞くのが好きなのですね。今回もダラダラした話で、どうもすみません。