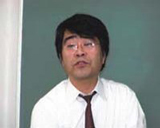明日のこころパート2
前回のタイトル「明日のこころ」というのは、昔聞いていた『小沢昭一の小沢昭一的こころ』というラジオ番組の最後のフレーズが「この続きはまた明日のこころだぁ!!」をふと思いだしたのでつけてみました。そんな古いの、だれが知ってるねん!
で、「新本格」についてです。推理小説の原型と言われるのが、エドガー・アラン・ポオの『モルグ街の殺人』で、そのあと、コナン・ドイルやチェスタートンを経て、アガサ・クリスティ、エラリー・クイーン、ディクスン・カーなどの長編本格ミステリが生み出されます。日本の推理小説では、なんといっても江戸川乱歩の名前が大きいのですが、「本格」と呼ばれるものは戦後の横溝正史が中心になるでしょう。豪邸の密室や孤島で起きる不可能犯罪に名探偵が挑む、というタイプが「本格」と呼ばれるものです。いわゆる「探偵小説」ですね。ところが時代とともに陳腐化し、リアリティのなさからも衰退していきます。そして登場したのが松本清張でした。社会派推理小説の誕生です。これは確かにリアリティがありました。しかし、当然のごとく「ワクワク感」がありません。みんなが社会派に飽きたころに起こったのが横溝正史ブームでした。『八つ墓村』はそれ以前に「少年マガジン」に載った影丸譲也による漫画で知っていたので、その二、三年後に角川文庫で出たときに、「ああ、あれか」と思い、すぐに読んだのですが、世の中ではあっという間にブームになりました。
もちろん、本格ミステリが完全になくなっていたわけではなく、都筑道夫や土屋隆夫などは、魅力的な作品を書き続けていました。で、横溝ブームをきっかけとして、「幻影城」という雑誌が創刊されました。四、五年で廃刊になってしまいましたが、探偵小説専門という、なかなかのすぐれものでした。泡坂妻夫や連城三紀彦がデビューしたのは、この雑誌からだったと思います。その後、綾辻行人のデビュー作『十角館の殺人』が出ます。「孤島の屋敷で起こる連続殺人」という、本格ものの王道で、ここから「新本格」と呼ばれる波が起こったのでした。やっと元にもどった。あー、しんど。
ただ、「新本格」の人たちは、トリックや構成はなかなかおもしろいのに、文章がウーンという人が多く、かなり読んだのに作品名が思い出せないのは、単に年をとってボケてきたからではないでしょう。中井英夫の『虚無への供物』など、今でもところどころ覚えている部分もあるぐらいで、文章がうまかった。『幻想博物館』『人形たちの家』など、耽美的な作品を数多く残しています。そういう人に比べると、新本格派は言葉のチョイスが雑な感じがして残念でした。
最近読んだもので、それほど期待しなかったのに意外に面白かったのは深緑野分という人。外国を舞台にした戦争もの、『戦場のコックたち』『ベルリンは晴れているか』は翻訳を読むような感じで、なかなかの文章力、構成力を感じさせました。『戦場のコックたち』は、主人公がアメリカ陸軍のコック兵で、ヨーロッパ戦線で戦いながら、「日常の謎」を解き明かすミステリーなのですが、最終的にはなかなか重厚な作品になっています。『ベルリンは晴れているか』は、ナチス・ドイツの敗戦後、恩人が不審死を遂げ、その殺害の疑いをかけられたドイツ人の少女が無実を証明するために、米ソ英仏の統治下に置かれたベルリンに向かうという話です。タイトルは、ナチス・ドイツがパリから敗退するときにヒトラーが言ったとされる言葉「パリは燃えているか」が元で、こちらは映画の題名にもなりました。ジャン・ポール・ベルモンドやアラン・ドロン、シャルル・ボワイエ、イヴ・モンタン、カーク・ダグラス、グレン・フォードなどが出ている超大作でした。
この二作がすばらしかったので期待して読んだ『この本を読む者は』は、同じ作者のものとは思われない作品でちょっとがっかり。ジャンルがまったく違うので、逆にどう持って行くのだろうと思ったのですが…。外れが全くない人というのもまあいないわけで、キングなど比較的安定していますが、それでもたまにがっかりということもあります。北欧の小説は比較的よいものが多く、スティーグ・ラーソンの『ミレニアム』は言うまでもなく、警察小説がいいですね。「マルティン・ベック」や「特捜部Q」、「クルト・ヴァランダー」のシリーズは非常におもしろい。「刑事ヴァランダー」のドラマも見応えがありました。BBC放映で、なんと主演はケネス・ブラナー。ローレンス・オリヴィエの再来と言われるシェークスピア俳優で、「ハリーポッター」ではロックハート先生を演じていました。
いわゆる推理小説の中でも名探偵ではなく、刑事が主人公になるものを警察小説と言います。本来地道な捜査をするのが刑事ですから、小説もやや地味めのものになります。日本では、横山秀夫が今最も売れています。『半落ち』『クライマーズ・ハイ』『臨場』『64』などが有名で、映像化された作品も多数あります。木村拓哉が主役を演じたのは、長岡弘樹の『教場』で、これも渋くてなかなかのものです。『教場』はまた月9でドラマ化されるようです。サングラスというより色つき眼鏡をかけた白髪の警察学校教官役のキムタクへの評価もなかなか高かったそうです。「何をやってもキムタク」と言われていたのが、チャラい感じを一切出さずに新境地を開いたわけですが、いつまでも「アイドル」というわけにもいかないでしょう。
日本でアイドルと言えば「熱狂的ファンを持つ『若い』歌手やタレント」ということでした。昔は「若い」という条件が必要だったのですが、いつしかアイドルの「高齢化」が始まりました。とくにジャニーズは「おっさんアイドル」だらけです。いくつまでアイドルとして存在できるのでしょうか。もちろん、加山雄三なんかは若大将と呼ばれ続けて、いつのまにか80歳をとっくに越えていますが。もともとアイドルは「偶像」という意味でした。宗教の中には偶像崇拝を禁止するものが多く、イスラエルの神から生まれたユダヤ教、キリスト教、イスラム教もその例にもれません。仏教も実は禁止していました。お釈迦様は仏像をつくるなとおっしゃったらしい。でも、拝むときに何もない空中へ向かって、というのもつらいので、昔の人はある工夫をしました。その工夫とは? これもまた明日のこころだ!