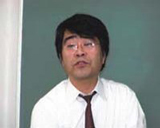明るくなるまで待って
「天勾践を空しうするなかれ時に范蠡なきにしもあらず」の范蠡は越王勾践の謀臣でした。范蠡は呉を滅ぼしたあと、用済みになった自分が勾践に疎んじられることを予見して職を辞します。「狡兎死して走狗烹らる」ということばはこのときのものです。その後、商人として大成功したとも言われます。ところが、日本へ逃げてきたという「トンデモ説」もあります。中国では、倭人は呉の太伯の子孫だと言っていました。長江のほとりにあった呉や越の人が日本にやってきた可能性は十分あります。稲作を伝えたのもそういう人たちかもしれません。范蠡たちがやってきた証拠に「呉」も「越」も日本の地名となって残っているではないかというバカバカしい説です。なるほど広島には「呉」があり、新潟・富山・福井のあたりは「越」です。
ただ、たしかに「呉」は「くれ」と読んで、大陸からやってきた人の祖国とされたことはあるようです。「呉服」という名字の人がたまにいますが、これは「くれは」と読むことがあります。「服部」は衣服をつくる朝廷の部民で「はたおりべ」と言いました。「はたおり」がなまって「はとり」「はっとり」となるわけで、「呉服」は「くれ+は(っとり)」ということでしょう。「くれのはたおりべ」ですね。「くれない」ということばも「呉の藍」がつまったものです。これらの「呉」は「中国」の代名詞として使われているようです。中国を代表する国としては他に「秦」があり、これが「支那」や「チャイナ」の語源になります。また、「漢字」とか「漢方薬」というように、「漢」も中国を意味します。「唐」という大帝国も当然、中国の代名詞ですね。「唐土」と書いて「もろこし」と読むのはちょっと変ですが。それらの国に比べると呉はローカルなのに、中国を代表する国のようになっているのは妙といえば妙です。
秦氏は秦の国と関係があるのかどうかはわかりませんが、渡来系であることはたしかなようです。室町時代の大名である大内氏が半島系であることははっきりしていますが、なんと長宗我部氏は秦氏ですね。講談の難波戦記でも大坂城にこもった武将の名を列挙するところで、長宗我部宮内少輔秦盛親と言っています。名字だけ見れば、蘇我氏の部民のような感じもしますが。朝廷だけでなく豪族の部民も存在しましたから。香宗我部氏というのもいます。長岡のあたりにいたのが長宗我部、香美のあたりにいたのが香宗我部です。土佐には七つの有力国人がいましたが、元親が幼いころには長宗我部は最弱だったようです。
長宗我部氏は四国を統一したあと、信長とトラブルがあったようで、本能寺の変の遠因にもなっているという説があります。元親は光秀の家老、齋藤利三と縁戚関係があり、光秀が信長との間で身動きがとれなくなったという説です。結局はその後、長宗我部氏は秀吉に屈して土佐一国の領土にもどります。さらに関ヶ原で敗れて、家はつぶれ、盛親は京都で寺子屋の師匠をしていました。お家再興を目ざしたのですが、結局かなわず、土佐国は山内一豊の領国になります。しかし、土佐には長宗我部の遺臣が多く、山内家は強引に滅ぼしたり、臣下に組み込んだりします。山内家の本来の家臣とは、上士・下士として差別されます。長宗我部系は下士・郷士になるわけで、坂本竜馬は郷士出身ですね。安岡章太郎の家もそうです。長宗我部の家臣に福留姓の者がいますが、福留功男も土佐出身なので郷士の出かもしれません。
大江健三郎の『万延元年のフットボール』に「チョーソカベ」ということばが出てきます。自分たちを守る「森」に襲ってくる者、という位置づけですが、カタカナ表記をすることで、異世界の妖怪のような雰囲気を漂わせています。大江健三郎は愛媛なので四国統一を目ざす長宗我部元親の軍勢を恐れた人々の記憶に「チョーソカベ」という名前が強く残されたのかもしれません。元寇の際、「蒙古高句麗がやってきた」といって怖れたことから、博多あたりでは、子供が泣き止まないときに「むくりこくりが来るぞ」と脅すようになったと言いますが、それと同じようなものでしょう。
大江健三郎は高橋和巳や倉橋由美子とともに、読んでいないとバカにされる、ということで一昔前の大学生はよく読んでいましたが、なんだかよくわからない文章で閉口しました。ただ、題名のセンスのよさだけは、山本夏彦だったかだれかがほめちぎっていたと思います。『芋むしり仔撃ち』とか『空の怪物アグイー』のように、わけのわからないものもあり、『死者の奢り』や『ピンチランナー調書』『同時代ゲーム』のような、ちょっとかっこよさげなものやら、『洪水は我が魂に及び』や『新しい人よ目覚めよ』のような、それはちょっと気取りすぎやろ、とつっこみたくなるものやら。『新しい人よ目覚めよ』はブレイクの詩を読み続けている「僕」を主人公とする短編連作集です。タイトルもブレイクの詩の引用です。大江健三郎はT・S・エリオットの詩を引用した作品も書いています。エリオットは『キャッツ』の原作者ですね。
「エピグラフ」というものがあります。「エビピラフ」ではありません。書物の巻頭に引用されている短い文ですね。「黙示録より」とか「シェークスピア」とか書いてあります。執筆者の意図の反映、内容の暗示でしょうが、エピグラフはこけおどしであることが多いようで、なくもがなです。あとで読み直しても、無理に書いておく必要もないのになあと思うことがしばしばです。本の最後にときどきある献辞・謝辞も無用ですね。作者にとっては特別の思いがあるのかもしれませんが、そこに書かれている人たちは読者にとっては全く無縁の人であり、作者のひとりよがりにすぎません。映画のエンドロールも、その点近いものがあります。情報としてあってもよいものは出演者の名前ぐらいで、あとはせいぜい監督の名前です。カメラマンとかスタイリストの名前、協賛した団体の名称など、一般の観客にとってはまったく必要ありません。こういうのも入れるべきだというのは西洋の考え方でしょうかね。エンドロールが流れた瞬間、明るくなっていないのに席を立つ人が多いのも当然でしょう。卑怯なのはエンドロール終了後におまけ映像が流れる場合があることです。しかも、それが劇中のあることがらの種明かしとか本当のオチになったりしていて、油断もすきもあったものじゃない。