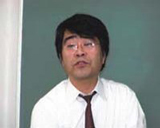モヤモヤーとして臭い
落語は、もともと正式な題名がないものもあったようで、だんだんと自然発生的についていったのでしょう。ですから複数の題名がついているものもあります。ネタバレになるものもあって、たとえば「肝つぶし」などは別の題名にしたほうがよさそうです。吉松という男が恋患い、友達がどこの娘だと聞くと、先日、呉服屋に買い物に行ったところ、番頭に邪険な客扱いをされた。店の娘が番頭を叱りつけ、買った物のほかに、反物を仕立てて長屋まで持って来てくれる。その夜、呉服屋の娘がやってきて、番頭のたくらみで、今晩仮祝言を挙げさせられると言う。娘の父親が死んでいるのをいいことに、娘を他家へ嫁がせ、店を乗っ取ろうとしている、今夜はここでかくまってくれと言うのだが、そこへ若い者を連れてやって来た番頭が、娘を引っ張って行ってしまう。手出しもできないまま、娘を奪われたくやしさに涙がこぼれる。そのとき、チーン、チーンという音で目が覚めたら二時やった、ということで、なんと全部夢の話。吉松が医者に聞くと、唐土の古い本に、夢の中の女に惚れて命が危うくなったときに、辰年の辰の月、辰の日、辰の刻のように年月揃って生まれた女の生き肝を煎じて飲ましたら、スッと治ったという話が書いてあると言う。両親を早くなくした友達は、吉松の親父からは息子同様に育てられた恩義があり、なんとか助けてやりたい。家へ戻って飯を食う気にもなれず酒を飲みだすのだが、妹のお花が年月揃った女であることに気づいてしまう。先に寝たお花の顔を見ながら、台所から持ってきた包丁を振り上げるが、妹のあわれさに涙をこぼすと、お花の顔に。目覚めた妹に、「仲間内で芝居をすることになって、寝てる女を出刃で殺す役が当たって稽古をしようと思うたんや」と言い訳をすると、お花は「ああ、びっくりした、肝が潰れた」「肝が潰れた? 薬にならんがな」という下げです。
下げの部分で聞き手はカタルシスを感じるので、前もってわかっているのはよくありません。もちろん、マニアになると、題名も下げも全部わかったうえで、話芸を楽しんでいるのでしょうが…。同じ落語で「死ぬなら今」というのは、その点、実に秀逸なタイトルです。演者は、なぜこの題名なのかは、しまいまで聴いたらわかるという仕組みになっていると強調してから始めることになっています。人を泣かせる阿漕な商いで身代を築いた船場の大店の赤螺屋ケチ兵衛さん、病となり、死を覚悟する。地獄行きは免れないとわかっているので、せがれに「三途の川の渡し賃を入れる頭陀袋に六文銭のほか百両入れてくれ」と頼みます。百両を閻魔大王への賄賂に使って、地獄から極楽に行かせてもらおうという魂胆です。ところが、葬式の時に親戚の叔父さんに見つかり、天下のお宝を土に埋めたらあかんと言われます。そこで芝居で使う小判を手に入れて、頭陀袋に入れます。ケチ兵衛さんは、閻魔大王に地獄行きを宣告されますが、例の百両を閻魔さんの袖の下に。閻魔さんの態度は一変して、「一代でこれほどの身代をなしたのはあっぱれ」と、極楽行きにしてしまいます。ところが、赤鬼や青鬼らも分け前をくれと騒ぎ出し、弱みを握られた閻魔さんは、赤鬼、青鬼らを引き連れて、冥土のキタとミナミで小判を使って遊び回ります。そのうち、その小判が極楽へと回ってきて偽小判とわかり、奉行所へ訴えられます。奉行はただちに特別機動隊を地獄へ派遣します。キタのバー「血の池」で盛り上がっていた閻魔さんたちは全員逮捕され、監獄行きとなりました。というわけで、地獄はいま閉店休業、「死ぬなら今」。下げをあらかじめ言っているのに、最後まで予想がつかない。最後の最後でタイトルが下げになるという鮮やかさ。米朝さんもやっていましたが、先代の文我でも聞いた覚えがあります。
「下げでカタルシス」と言いましたが、「延陽伯」の下げはいまでは通用しなくなって、カタルシスどころかきょとんとしてしまう人もいるかもしれません。東京では「たらちね」という題で演じられる話ですが、長屋に住む独り者のところに縁談がもちこまれます。京都のお公家さんのところへ奉公していたということで、ことばが丁寧すぎるという女の人。「わらわこんちょう、たかつがやしろにさんけいなし、まえなるはくしゅばいさてんにやすろう。はるかさいほうをながむれば、むつのかぶとのいただきより、どふうはげしゅうしてしょうしゃがんにゅうす」という具合。そのあと男は銭湯に行くのですが、このあたりの描写は枝雀がやはり面白い。夜に女がやってきて、名前を聞くと、「なになに、わらわの姓名なるや?」「あんた、わらやの清兵衛はんちゅうんですか? 男みたいな名前でんなぁ」「これは異なことをのたもう。わらわ父は元京都の産にして、姓は安藤、名は慶三、あざなを五光と申せしが、我が母、三十三歳の折、ある夜丹頂を夢見て、わらわを孕みしが故に、たらちねの胎内をいでし頃は鶴女、鶴女と申せしが、これは幼名、成長ののちこれを改め延陽伯と申すなり」というやりとりも面白い。翌朝、枕元に手をついて、「あ~ら我が君、もはや日も東天に輝きませば、お起きあって、うがい手水に身を清め、神前仏前に御あかしをあげられ、朝餉の膳につき給うべし。恐惶謹言」「飯を食うことが恐惶謹言か。そしたら、酒飲んだら酔ってくだんの如しやな」という下げ。いまどき、「恐惶謹言」も通じないし、「よってくだんのごとし」も意味不明でしょう。もともと関西弁にもなっていません。かといって「酔うて」とすると、ますます意味がわかりにくくなります。下げが通じにくくなった話は演者によって、いろいろ変更を加えられています。
「頭山」の下げはシュールで今でも通用する魅力的なものです。ケチな男が、もったいないとさくらんぼの種まで食べたところ、そのさくらんぼの種は腹の中で根をはり、やがて頭の上に芽を出して大きく育っていきます。春になると花が咲いたので、大勢人が集まり、頭の上で花見を始めました。ドンチャン騒ぎに怒った男は桜の木を引っこ抜いてしまいます。すると頭の真ん中に大きな窪みができてしまい、表で夕立にあったとき、穴に水が溜まって池になりますが、ケチな男はその水を捨てようとしません。やがて、その水にボウフラが湧き、それを餌にして鮒やら鯉やら湧いてきました。それを聞きつけて大勢釣りにやってきます。朝から晩まで大騒ぎ、ケチな男はこんなにうるさくてはたまらんと、その池にドッボーン。上方では、「さくらんぼ」という題で枝雀がやっていましたが、「おい、芳、いてるか」というセリフで始まる細かい場面を積み重ねるという凝った作りで、結構長い話にしていました。下げも夫婦で飛び込む形になっています。これは枝雀の理論「緊張の緩和で下げになる」があてはまりません。むしろモヤモヤ感が残ります。