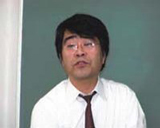徳川首相
少し前に話題になったものとして、小泉構文なるものがあります。同じような内容を繰り返すパターン、循環論法と言うか、トートロジー(同語反復)と言うか、長々と語っても情報量は半分、場合によってはゼロ、でもなぜかポエムのような言い回しが妙に魅力的です。「今のままではいけないと思います。だからこそ日本は今のままではいけないと思っています」とか「三十年後の自分は何歳かなと震災直後から考えていました」とか「2月ってことは、あと1年でまた2月がくる、ということです」、「このプレゼント、頂き物なんです」、「今日はあなたの誕生日ですか。私も誕生日に生まれたんです」、「夜景を見るなら、断然夜をおすすめします」…。場合によっては、悪意をもって切り取られている可能性がなきにしもあらずですが、小泉さんの場合は確かに言ってそうです。
安倍さんや石原慎太郎などは悪意をもって切り取られることがよくありました。演説を妨害されたときの「あんな人たちに負けるわけにはいかない」とか「選挙のためならなんでもする」とか「100パーセント正当化するつもりはない」の「はない」をカットされた件とか。石原慎太郎はタカ派の政治家としてしか知らない人も多いようですが、もともとれっきとした小説家です。映画化された作品も多く、弟の裕次郎がデビューしたのも慎太郎原作の映画です。テレビドラマで「青春シリーズ」というのが大昔ありました。その最初の作品が『青春とはなんだ』で、裕次郎主演の映画をテレビに持ってきたものです。この原作者が石原慎太郎でした。高校のラグビー部を舞台にした、学園ものの「はしり」で、このシリーズは大ヒットしました。しかし、しだいに人気にかげりが出て、シリーズが打ち切られたころ、なんと小学校を舞台にしたものも生まれました。先生役は水谷豊です。さらに中学を舞台にした学園ものもはやります。金八先生ですね。最初のシリーズに出ていた田原俊彦ものちに『教師びんびん物語』というドラマで小学校の先生役をしています。徳川龍之介という役名でした。
しかし、なんと言っても学園ものの先生といえば、坂本金八でしょう。名字は武田鉄矢の好きな坂本竜馬からのパクリで、下の名前は金曜八時のドラマなので略して金八、という安易なネーミングです。昔の商人も、こういう省略形が呼び名になっている人が多いですね。紀伊国屋文左衛門が「紀文」、奈良屋茂左衛門が「奈良茂」、灘屋萬助が「なだ万」。そういえば「ジョン万」という人もいました。なぜか名前は省略されるんですね。古くは榎本健一がエノケン、阪東妻三郎がバンツマ。キムタクやマツケン、クドカン、ケンコバなどもこの延長線上にあります。「せんだみつお」という人は逆に「せんみつ」という言葉を名前らしく改めたものです。ところがこの「せんみつ」は「千のうち本当のことは三つしか言わないうそつき」を短く表した言葉だというのがややこしい。
言葉巧みに人を言いくるめるという意味で、弁護士をののしるときに「三百代言」と言っていたことがあります。本来は代言人つまり弁護士の資格をもたずに、他人の訴訟を扱う「もぐり」の人間を言いました。「三百」は特に意味がなく、多いということを表しているのでしょう。多いことを表す数字としては「八百」もよく使います。「うそ八百」とか「八百万の神々」というように。「白髪三千丈」の「三千」というのもありますね。千手観音の手は千本ちょうどというわけでもないようです。千より少ないこともあるとか。仏像によっては顔がいくつかついているものもあります。「八面六臂」というのはあちらこちらの方向へ向かって活躍することですが、顔は八つですね。「臂」はひじのことなので「六臂」は六本腕ということになります。興福寺の有名な阿修羅像は三面六臂ですね。腕が細長いのでタカアシガニを連想するという人もいました。六本ということに注目して、あれは昆虫ではないかと言った人もいます。とくにあの六本の配置は甲虫系のイメージです。エジプトでもスカラベというのがありました。
百足となるとムカデですね。これは足が百本あるということでしょうか。靴一足は、左右の両足分をまとめて数えるのだから、百足は二百本なのか。いずれにせよ、「百」に意味があるわけではなく、多いということを表しているだけなのでしょう。武将の兜にムカデをデザインしたものがありますが、グロテスクな感じで脅かそうというより、後ろ向きに行けないところから前へ突進する勇ましさと結び付いたと言います。トンボのデザインも同じ理由かもしれません。日本の武将は、鎧と兜は身にまとっていますが、盾を持たないのはなぜでしょう。槍や矢、ときには石などを防ぐには盾はふさわしいのですが、刀を防ぐ感じはありません。騎馬武者同士の闘いは槍がメインだったようですが、最終的に刀を使うこともありそうです。槍を武器にするのなら両手が使えるほうが便利だし、弓矢なら盾はむしろ邪魔です。馬を下りての接近戦になると刀ですが、鎧がしっかりしていれば盾の意味は薄そうです。
鎧通しという専用武器もあるようですが、鎧のすきまを狙う必要があるでしょう。馬上の武者を倒すには、下から槍で狙って太もものあたりを刺す、というやり方もあったようです。兜を割って敵を倒すというのは、日本刀では無理な感じがします。据え物切りと言って、動かずに置かれていたらうまく行くこともあるようですが、それでもなかなか難しい。明治以降では最後の剣豪と言われた榊原鍵吉が成功しています。明治になっても『るろうに剣心』のような侍はいたのですね。ただし、剣心のモデルは河上彦斎と言われています。中村半次郎、岡田以蔵とともに幕末の三大人斬りと言われた人です。こんなものにも「三大」があるというのもなんだかなあ、です。中村半次郎は維新後桐野利秋と名乗って西郷隆盛の片腕となり、西南戦争で討ち死にします。
では、史上最強の剣豪はだれでしょう。卜伝とか一刀斎とか御子神典膳とか、有名な剣豪は数多くいます。時代を無視してそういう剣豪が一堂に会したら、という「剣豪オールスター」みたいなのが、「寛永御前試合」と言われるものです。家光の御前で試合をする、というやつです。そういえば、家康が総理大臣になるという、ばかばかしい映画がありました。当然SF設定なのですが、原作はビジネス小説と銘打たれており、後半部分はダレ気味でした。